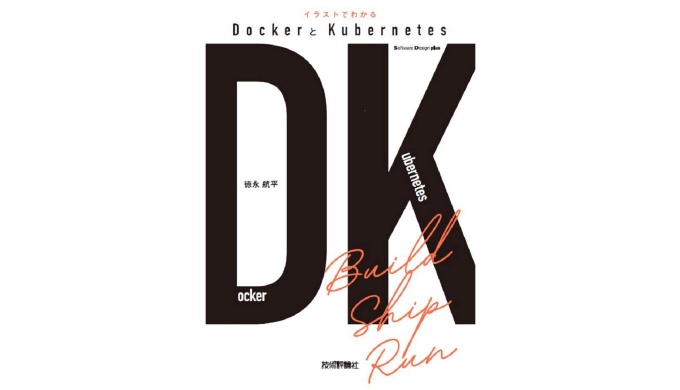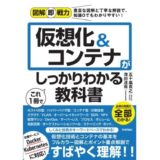技術評論社が発行しているOSとネットワーク,IT環境を支えるエンジニアの総合誌「Software Design」編集部が自信を持ってお届けする書籍シリーズ「Software Design plus」よりDockerとKubernetes解説本が登場。
コンテナ技術に始めて触れる方を対象に、さまざまなシステムで利用されていDockerとKubernetesの基本的な機能の概要や各ツールの持つ基本的な機能、コンテナの構造やDockerとKubernetesがコンテナを作る仕組みを豊富なイラストで解説しています。
目次
「イラストでわかるDockerとKubernetes」の概要
内容の抜粋
Dockerとkubernetesは、ます。仮想化とは違うので、エンジニアの皆さんもそのメリットをどう活かしていくのか悩ましいところです。
本書は、Dockerとkubernetesのしくみを大胆にイラスト化。視覚的に理解することができるので、その技術の本質を理解しやすくなります。各所でコマンド入力を利用してDockerとkubernetesの動作もわかるようになります。
Dockerとkubernetesのしくみを根底から知りたい方、理論をしっかり理解したい方、インフラエンジニア、ネットワークエンジニア、システムエンジニア、プログラマにおすすめ。
著者
徳永航平
日本電信電話株式会社ソフトウェアイノベーションセンタ所属。1993年生まれ。2018年の入社以来,コンテナ技術とオープンソースソフトウェア(OSS)に関する活動に従事。現在は,CNCF containerdのサブプロジェクトStargz Snapshotterのメンテナを務めながら,コンテナイメージを高速に配布する技術(lazy pull)に取り組む。また,コンテナランタイムに焦点をあてたコミュニティミートアップContainer Runtime Meetupを共同運営している。
目次
- 第1章 コンテナ技術の概要
- 1-1 コンテナを見てみよう
- 1-2 コンテナ技術の基本的な特徴
- 1-3 本書で注目するDockerとKubernetes
- 第2章 Dockerの概要
- 2-1 DockerによるBuild、Ship、Run
- 2-2 コンテナのレイヤ構造
- 2-3 DockerのアーキテクチャとOCIランタイム
- 2-4 まとめ
- 第3章 Kubernetesの概要
- 3-1 Kubernetesの特徴
- 3-2 Kubernetesクラスタとkubectl
- 3-3 Kubernetesにおける基本的なデプロイ単位
- 3-4 KubernetesにおけるPod群のデプロイにまつわるリソース
- 3-5 設定項目やボリュームに関するリソース
- 3-6 Kubernetesにおけるサービスディスカバリ
- 3-7 KubernetesのPodとCRIコンテナランタイム
- 3-8 まとめ
- 第4章 コンテナランタイムとコンテナの標準仕様の概要
- 4-1 コンテナランタイムと2つのレイヤ
- 4-2 いろいろな高レベルランタイム
- 4-3 いろいろな低レベルランタイム
- 4-4 OCIの標準仕様
- 4-5 runcを用いたコンテナ実行
- 4-6 実行環境作成に用いられる要素技術
書籍情報
- 発売日 : 2020/12/5
- 仕様:A5判・148ページ
- ISBN-10 : 4297118378
- ISBN-13 : 978-4297118372
- 出版社: 技術評論社
- 価格:2,280円+税
- 電子版:あり
リナスクレビュー
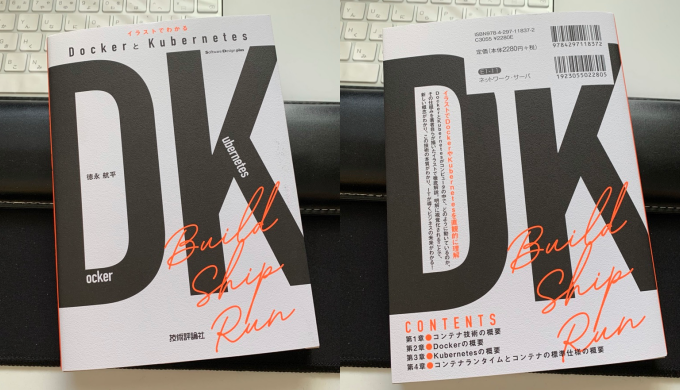
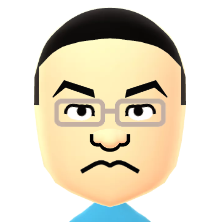 エスパくん
エスパくん- LinuCレベル1 Version10.0で出題範囲に新たに加わった仮想マシン・コンテナの概念や、LinuCレベル2 Version10.0で出題範囲に新たに加わった仮想化サーバーとコンテナの理解を深めるのに役立つ書籍。
- 豊富なイラストでコンテナの構造やワークフローをわかりやすく解説しています。コマンドの実行例も掲載されており、実際の動作検証を行うことで理解を深めることができます。
- 130ページほどの本なので短時間で読めてますが、内容はかなり高度なのである程度の予備知識があった方が読みやすいです。事前にLPI-Japanが提供しているversion 10.0差分学習教材に一通り目を通しておくことをおすすめしたいです。
- Ubuntu 20.04上でDockerを導入する方法の解説もありますが、本番環境への使用が推奨されていないget.docker.comのスクリプトを用いたインストール方法となっています。
- この本以外にもおすすめの仮想化コンテナの解説本が多数出版されているので追って紹介します。
- 豊富なイラストでコンテナの構造やワークフローをわかりやすく解説
- LinuC Version10.0で出題範囲に新たに加わった仮想マシンとコンテナについて理解を深められる
- ページ数は少ないものの内容はかなり高度なのである程度の予備知識が必要
- Dockerの導入の解説が限定的なので自力で準備する必要あり